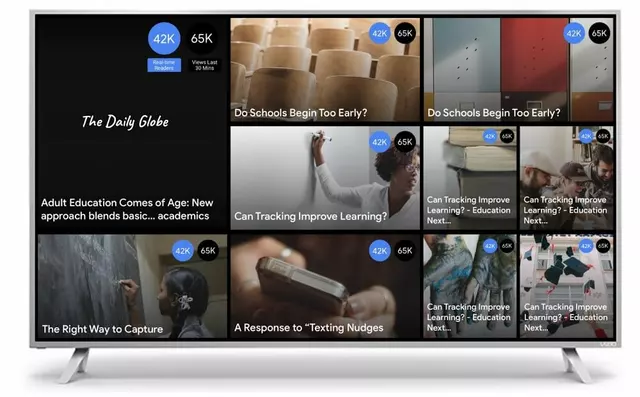インドネシアのセラミック産業で、政府の保護政策が直接的にOEM(オリジナル・イクイップメント・メーカー)生産を押し上げている。インドネシア・セラミック協会(ASAKI)は17日、国内工場でのOEM製造が急増していると発表した。その背景には、輸入品の急増に対応するための貿易制限と、生産基盤の近代化を組み合わせた「包摂的な産業戦略」がある。ここ数年、タイルや衛生陶器の生産現場で、手作業から半自動化への転換が着実に進んでいる。その先頭に立つのは、政府の資金支援と規制の組み合わせだ。
貿易保護から生産革新へ:政策の転換点
2020年5月27日、インドネシア貿易産業省は、中国やタイからのセラミックタイル輸入が急増したとして、200日間の暫定セーフガードを発動。1キログラムあたり3ペソ(約6.6円)の追加関税を課した。だが、その後の関税委員会の判断で、この措置は「不発動」とされた。それにもかかわらず、政策の影響は消えなかった。むしろ、一時的な関税以上に、インドネシア・セラミック協会(ASAKI)が指摘する「SNI(インドネシア国家規格)の強化」「アンチダンピング調査の継続」が、輸入品の品質・コスト面での競争力を鈍らせた。結果として、国内メーカーは「安かろう悪かろう」の輸入品に頼らず、自社ブランドやOEMで市場を奪還する道を選んだ。
資金支援が生産性を変える:サウ・ムン社の事例
その象徴が、中部ジャワ州にあるサウ・ムン社だ。同社は、工業貿易省が管轄する産業振興基金から2,800万ドン(約270万円)の補助を受け、6,000万ドン相当のエアコンプレッサーを導入した。この一歩で、成形・泥散布・洗浄の工程が30%高速化。製品の滑らかさと輝きが劇的に向上した。取締役のフイン・キム・トゥイ氏は、「この支援の価値は、機械を買うことじゃない。手作業から半自動化へ、環境にも経済にも優しい生産モデルへの転換を促したことだ」と語る。これは単なる設備投資ではなく、生産哲学の変革だ。
政府は23の陶磁器企業に合計2兆7,620億ドン(約250億円)の支援を実施。2025年にはさらに10社に12億7,000万ドンを割り当てる予定だ。資金は、機械の購入だけでなく、従業員の技術研修や、SNI適合性のための検査設備の整備にも使われている。ここに「単なる保護」ではなく、「競争力の育成」の意図が見える。
国際競争力の鍵:CBAMと日本の市場
インドネシアの動きは、単なる国内政策ではない。2025年2月、EUが本格導入を検討するCBAM(炭素国境調整メカニズム)への対応でもある。CBAMは、炭素排出量の高い製品に追加課税する仕組みで、インドネシアのセラミック輸出が大きな影響を受ける可能性があった。政府は、国内生産の電力源を再生可能エネルギーに切り替えることで、CBAMの炭素コストを抑える戦略を並行して進めている。もしCBAMが「炭素リーケージ防止」に失敗すれば、代わりにEUのETS(排出権取引制度)の無償割当を求める方針だ。つまり、インドネシアは「輸出産業の生存戦略」を、国内生産の強化と結びつけている。
この動きは、日本の市場にも影響を及ぼしている。日本では、日本セラミックタイル市場が2025年から2032年にかけて年平均7.2%の成長が見込まれる。その背景には、インドネシアの品質向上と安定供給が大きく寄与している。特に、低価格・低品質の中国製品から、信頼できるOEM製品へのシフトが進んでいる。日本の建材業界は、インドネシアの政策転換を「ポジティブなトレンド」と評価している。
日本のセラミック産業とのつながり
インドネシアのセラミック産業が強化される一方で、日本ではより高度なセラミック技術が進化している。ノリタケは、スマートフォンや電気自動車、AIサーバーに不可欠な積層セラミックコンデンサ(MLCC)の材料を主力としている。NGKも、独自のセラミック技術で、医療機器や宇宙機器への応用を広げている。これらは「高付加価値」の分野だが、インドネシアのOEM増加は、その下流の「量産型セラミック」の供給基盤を安定させる効果がある。つまり、インドネシアが「量」を支え、日本が「質」を支える——両者の関係は、競合ではなく、補完的になってきた。
2025年以降の展望:OEMの本格化と雇用の変化
ASAKIは、2025年までにセラミック産業のバリューチェーン全体を改善するプロジェクトを進めている。生産設備の導入だけでなく、物流・流通の効率化、ブランド構築にも力を入れる。その結果、2025年以降は、単なるOEM生産から「自社ブランドの海外展開」へとステップアップする企業が増えると予想される。
雇用面でも変化が起きている。機械化により、単純労働者の数は減少しているが、その分、機械操作や品質管理の技術者が必要とされている。若年層の職業選択にも影響を与え、工業高校や職業訓練校でのセラミック技術科の志願者が増えているという。
もはや、インドネシアのセラミックは「安価な輸入代替品」ではない。技術力と政策の両輪で、東南アジアの生産拠点としての地位を固めつつある。今後、日本企業がインドネシアのOEMメーカーと提携するケースが増えるのは、時間の問題だろう。
Frequently Asked Questions
インドネシアのセラミックOEM増加は、日本の輸入にどう影響する?
インドネシアのセラミック製品は、品質と価格のバランスが改善され、日本市場への輸入が増えています。特に、中国製の低品質品に代わって、SNI認証を取得したOEM製品が建材業界で評価され、2025年以降の輸入量はさらに増加すると見込まれます。日本の業者は、安定供給とコスト競争力の両立を求めて、インドネシアメーカーとの提携を強化しています。
なぜ政府はセーフガードを発動した後に撤回したのに、効果があったの?
セーフガード自体は撤回されましたが、その発動が輸入業者に「リスクがある」というメッセージを送りました。結果として、輸入量は一時的に減り、国内メーカーはその隙を突いて生産体制を整えました。その後のSNI規格強化や補助金政策が、持続的な競争力向上につながったのです。一時的な措置が、長期的な産業変革のトリガーになったのです。
サウ・ムン社の成功は他の企業にも真似できる?
はい。サウ・ムン社の事例は、小規模企業でも政府補助金を活用して生産性を飛躍的に上げられることを示しています。2,800万ドンの補助で6,000万ドンの設備を導入できたのは、政府の補助率が50%以上だったからです。同様の支援制度は23社に適用されており、特に中小企業にとって、技術革新のハードルを下げた画期的なモデルです。
CBAMとインドネシアのセラミック政策の関係は?
EUのCBAMは、炭素排出量の多い製品に追加課税する仕組みです。インドネシアは、セラミック生産に使う電力を石炭から再生可能エネルギーに切り替えることで、炭素排出を削減し、CBAMの課税を回避しようとしています。これは単なる環境対策ではなく、輸出市場を守るための経済戦略です。
日本のセラミック企業はインドネシアとどう関わっている?
日本企業は、インドネシアのOEMメーカーに高精度なセラミック原料や製造装置を供給しています。ノリタケやNGKは、直接的な投資は少ないものの、技術協力や品質指導を通じて、現地の生産基盤を支えています。将来的には、日本企業がインドネシアでOEM生産を委託するケースも増える可能性があります。